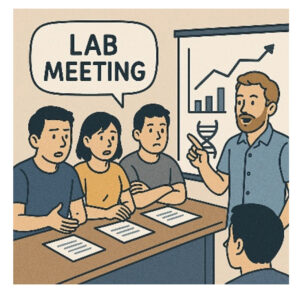コラム
留学生活④ ラボミーティング、その後、日本人会議
私が留学していた研究室では、2週間に1回、1~2時間ほどの研究室会議(ラボミーティング)が定期的に開かれていました。教授の前で、自分の研究の進捗状況、特に前回のラボミーティング以降に行った実験の経過や結果を、研究者が順番に報告します。教授はその発表にコメントをし、次に行うべき実験について研究者と相談したり、指示を出したりするという形式でした。
担当者1人あたりの発表時間は通常15分ほどでしたが、議論が白熱すると30分近くかかることもありました。もちろん全て英語で進められるため、教授だけでなく欧米から留学している研究員が全員聞いている中で発表を行うのは、毎回かなりのプレッシャーでした。2週間ごとなので、毎回良い結果が出るわけではなく、実験がうまくいかず発表内容が乏しいときなどは、特に辛い時間でした。普段は私たちに合わせてゆっくり話してくれる教授も、討論が熱を帯びるとナチュラルスピードの英語になり、質問の内容を理解できずさらに追い詰められることもよくありました。
日本人研究者によく見られる傾向として、分からないときや緊張しているときに曖昧な返事をしてしまうことがあります。私たちも例外ではなく、そのために教授からの指示を正確に理解できないことがありました。その結果、次のラボミーティングで教授の意図と異なる実験結果を報告してしまい、「この2週間、何をしていたの?」という気まずい雰囲気になることもありました。
「このままではいけない」と思い、同じ研究室に留学していた日本人の先生と、ラボミーティング終了後に自主的に集まり、お互いに教授から何を言われたのか、指示の内容を確認し合うことにしました。この“日本人会議”は、自分では気づかなかったことや曖昧に理解していた点を整理するうえで非常に有効でした。教授と英語で直接やりとりしていると、緊張のせいで意外と多くのことを聞き落としていることにも気づきました。ラボミーティング後に日本人が集まって真剣に話している姿は、他の研究者たちから冗談交じりに “Japanese Meeting” と呼ばれていましたが、実際には指示内容を正確に理解し、効率的に研究を進めるための大切な時間でした。
アメリカでのラボミーティングを通して痛感したのは、教授の話や指示を曖昧に理解したまま自分の解釈で実験を進めると、時間と研究費を無駄にしてしまうということです。そこで私は、必ず自分の言葉(英語)で「私がやろうとしているのはこういうことですが、これでよいですか?」と確認するようにしました。たとえ「今さらそんなことを聞くのか」と思われるかもしれなくても、恥を忍んで確認するようにした結果、コミュニケーションが格段に良くなり、研究も順調に進むようになりました。
もう一つ学んだことがあります。私の専門は病理学でしたが、教授は分子生物学が専門だったため、組織学的な実験では「この方法のほうが良いのではないか」と感じることがありました。そのような場合には、まず教授の指示どおりに実験を行い、そのうえで自分の考えた方法も追加で試してみるようにしました。今思えば、教授はプロジェクト全体を俯瞰して、最も必要な実験を選んでいたのだと思います。もし私が勝手に実験の方法や順番を変えていたら、たとえ良い結果が得られても、研究の流れを整理して進めるうえで支障になっていたかもしれません。これは自分が指導者の立場になってから、改めて理解できたことです。 T. I.